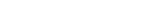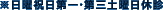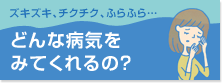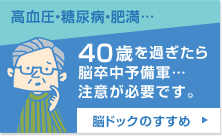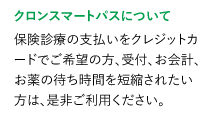11/22,
2025
【24】片頭痛とまぶしさ 続編―光は本当に敵か?
「まぶしい光を見ると片頭痛が起こる気がする」「明るいところにいると頭がズキズキしてくる」――そう訴える患者さんは少なくありません。以前のコラムで「片頭痛とまぶしさ」の関係についてご紹介しました(2024年1月14日)。今回はその続編として、“まぶしさ”とどう向き合えばよいかを、わかりやすく掘り下げてみたいと思います。
まぶしさ=片頭痛の引き金?…実はそれだけではありません
まぶしさ(光過敏)は片頭痛の「引き金(トリガー)」とよく言われますが、最新の研究では、「まぶしさが本当に発作を引き起こしているのか?」をもう一度見直す動きがあります。というのも、実際には片頭痛の発作の“前触れ”として、すでに光に敏感になっている状態(予兆)のことが多いからです。つまり、「光がまぶしいと感じたから頭痛が起きた」のではなく、「もうすぐ片頭痛が始まりそうなときに、光に対して敏感になっていた」――というのが実際のところなのです。つまり、「光を浴びた=必ず片頭痛になる」という単純な話ではないのです。
「光を避けすぎる」ことの落とし穴
片頭痛持ちの方の中には、外出時にいつもサングラスを手放せない方も多いと思います。確かに、強い太陽光や、ちらつきのある照明、青白いLEDなどにさらされると頭痛が悪化することもあります。ですが、必要以上に光を避け続けることには注意が必要です。
人間の目は、暗い環境に長くいると、より光に敏感になります。つまり、いつも薄暗い場所や濃いサングラスの中で過ごしていると、ちょっとした明るさでも耐えられなくなってしまう可能性があるのです。これを「暗順応」といいます。実際、患者さんの中には「最初は外出時だけだったサングラスが、今では室内でも手放せなくなった」とおっしゃる方もいます。それが「光過敏の悪循環」を招いていることもあるのです。
光とうまくつき合う、という考え方
まぶしさがつらいときは、サングラスや遮光レンズを使うことは有効です。特に、青い光を抑えるレンズ(FL-41フィルターレンズなど)は、光過敏の強い方に向いていると言われています。ただし、「光=悪」と決めつけないことが大切です。
例えば、最近の研究では、緑色のやわらかい光は片頭痛を悪化させにくく、むしろ落ち着く効果がある可能性が示唆されています。また、暗くしすぎず、やわらかい光で過ごすようにすると、脳が光に少しずつ慣れ、まぶしさに対する過敏さが改善されることもあります。さらに、片頭痛の新しい予防薬(CGRP関連製剤で現在3種類の皮下注射薬があります。さらに近々、新たに錠剤の発売が予定されています。)では、「光に対する敏感さがやわらいだ」と実感する患者さんも増えてきています。まぶしさがつらい方は、薬の見直しも検討すると良いかもしれません。
正しく知ることが、片頭痛とうまく付き合う第一歩
片頭痛とまぶしさの関係は、非常に奥が深く、患者さん一人ひとりの感じ方も違います。ですが一つ言えるのは、「光を恐れるあまり、生活の楽しみまで減らしてしまわないようにする」ことが大切だということです。
・発作時は暗い部屋で休んでOK
・でも普段は、少しずつ自然な光にも慣れていくこと
・光が本当に引き金なのか、日記をつけて確かめてみること
・不安なときは、専門医に相談すること
こうした工夫を通じて、「必要なときは光を調整しつつ、普段はなるべく自然な光と共に過ごす」というバランスの取り方が、まぶしさと上手につき合っていくヒントになるかもしれません。